
家賃を見直したいと思っても、入居者に拒否される可能性があるため、「どこまでできるのか」「どう進めればいいのか」と悩むオーナーは少なくありません。
家賃の値上げには、法的なルールと段階的な手順があり、合意なしに一方的に進めることはできないのが原則です。

株式会社Vision Bridge 専務取締役 /COO
不動産コンサルタント
東 将吾(Higashi Shogo)
大学卒業後、新卒で東証一部上場企業の商品企画、マーケティング職を経験。その後、大手出版社にて企画営業に従事する。2017年に売買仲介をメイン事業とする不動産会社に入社し、賃貸管理事業部の責任者としてゼロスタートから投資家100名超、約2,000戸の物件運営に携わる。その後同社執行役員に昇格し、複数の新規事業を牽引。IT×不動産、企業DXを推し進める。 2022年に株式会社Vision Bridgeを設立し専務取締役に就任。
本記事では、不動産管理のプロが、値上げの基礎知識から準備のポイント、入居者に断られた場合の対応、調停・裁判といった法的フローまで、実践的な手順を丁寧に解説します。
※法的な交渉の相談・対応については弁護士に相談してください。
家賃を上げる前に知っておきたい3つの大事なこと

家賃の値上げを進めるにあたっては、法的な前提や入居者とのやり取りの進み方をしっかり理解しておくことが大切です。
感覚だけで進めてしまうと、思わぬトラブルにつながることもあるため、あらかじめ基本のルールや流れを把握しておきましょう。
家賃の増額交渉に関して、特に重要となるポイントは、以下の3つです。
・入居者が家賃の値上げを断っても、違法ではない
・オーナーにも正当に値上げを求める権利がある
・全体の流れを先に把握しておくと安心
ここからは、それぞれの項目について、詳しく見ていきましょう。
入居者が家賃の値上げを断っても、違法ではない
家賃の値上げは、オーナーが一方的に決められるものではなく、入居者との合意が必要です。

不動産管理コンサルタント
東 将吾
入居者が値上げを断った場合でも、そうした「拒絶」が違法とされることはありません。
新しい家賃を適用するには、交渉を経たうえで合意に至ることが前提となります。
入居者は借地借家法に守られている
借地借家法第32条では、以下のように示されています。
建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。
引用元:借地借家法(平成三年法律第九十号)
つまり、合意がない場合、最終的には裁判に委ねられることを示しており、「合意しなければ強制的に家賃は上げられない」ことを意味します。

不動産管理コンサルタント
東 将吾
入居者が値上げを拒否したからといって、それ自体が違法になるわけではありません。
借地借家法は、借りている方の立場を守るための法律です。
そのため、入居者が家賃の値上げに同意せずに断ることも、法律のルールにのっとった正当な対応だといえます。
オーナーにも正当に値上げを求める権利がある
家賃の値上げについては、借主が拒否する権利を持っている一方で、オーナーにも正当に請求する権利があります。
借地借家法第32条では、以下のように示されています。
建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。
引用元:借地借家法(平成三年法律第九十号)

不動産管理コンサルタント
東 将吾
つまり、経済の変化や周辺の家賃相場とのズレがあるときは、オーナーが今後の家賃について見直しを求めることが、法律で認められているのです。
オーナーが家賃値上げを請求できるケース
以下のような状況では、家賃の増額が正当となる可能性があります。
・固定資産税や都市計画税など、維持コストが増えた場合
・周辺地域の家賃相場と大きな差がある場合
・建物の老朽化によって修繕費・管理費などが増えている場合

不動産管理コンサルタント
東 将吾
こうした客観的な根拠を示すことで、入居者との交渉も進めやすくなり、家賃の見直しについて理解を得やすくなります。
注意:請求はできても、必ず通るとは限らない
借地借家法では、家賃の増額を「請求する」ことは認められていますが、請求しただけで家賃がそのまま変更されるわけではありません。

不動産管理コンサルタント
東 将吾
実際に増額が適用されるかどうかは、入居者との合意や、必要に応じて調停・裁判で判断されることになります。
そのため、感情的な理由ではなく、経済状況の変化や周辺の家賃相場との差など、客観的な根拠と資料をもとに請求を行うことが大切です。
全体の流れを先に把握しておくと安心
家賃の値上げは、オーナーが通知しただけで決まるものではなく、入居者との話し合いを重ねながら、いくつかの段階を踏んで進んでいきます。
あらかじめ流れを知っておくことで、「どう対応すればいいのか分からない」という不安を減らし、落ち着いて判断しやすくなります。
家賃値上げの基本ステップ(7段階)
家賃の増額交渉は、主に以下のような流れで進んでいくことが多いです。
- 値上げ打診(通知・口頭または文書での提示)
- 入居者の拒否(1回目の拒否)
- 妥協案の提示(条件の再提案)
- 入居者の再拒否(2回目の拒否)
- 法定更新または調停への移行
- 調停による話し合い
- 裁判(調停が不調に終わった場合の最終手段)

不動産管理コンサルタント
東 将吾
このように、家賃の値上げ交渉は段階を追って進めていくもので、すぐに結論が出るものではありません。
値上げの打診に対してすぐに合意されることもあれば、何度かのやり取りを経てようやく合意に至ることもあります。
調停や裁判に進むのは最終手段であり、実際には初期の交渉段階で合意に至る割合が多くなっています。
家賃値上げの準備として必要な3つのこと


不動産管理コンサルタント
東 将吾
「何から始めればいいのか分からない」と感じるときこそ、落ち着いて準備を整えることが大切です。
根拠と状況に基づいて準備を進めることで、不安を軽くしながら、入居者との交渉にも自信を持って臨めるようになります。
値上げ通知の前に、オーナーとしてやっておきたい3つの準備として、以下が挙げられます。
・値上げの正当な理由を裏付ける資料をそろえる
・契約書と特約条項をもう一度チェックする
・家賃相場と自物件の条件を比較する
ここからは、それぞれの準備について、詳しく見ていきましょう。
1. 値上げの正当な理由を裏付ける資料をそろえる

不動産管理コンサルタント
東 将吾
家賃の値上げ交渉のスタートラインに立つためには、家賃を見直したいと思った理由を裏付けるための資料を手元にそろえておくことが大切です。
「修繕費が増えた」「税金の負担が重くなった」といった事情も、数字で示せる形にしておくことで、説得力のある交渉につながります。
必要な書類を具体的に集める
入居者に対し、値上げの理由を裏付けるためには、次のような書類をあらかじめ用意しておくと安心です。
・固定資産税や都市計画税の通知書
・建物や設備の修繕費・管理費の明細
・周辺エリアの家賃相場資料(不動産サイトの募集情報や、リサーチ業者による調査データなど)
こうした情報があることで、数値や実情に基づいて丁寧に判断していることが伝わりやすくなります。
書類はあくまで「交渉用」に自分で手元に置く
用意した書類は、交渉の場でそのまま入居者に見せるものではありません。
あくまで、オーナー自身が「なぜ家賃を見直したいのか」を整理し、交渉の根拠として備えておくための資料です。
数字や実例をもとに冷静に判断するための準備材料として、手元に置いておくことを基本としましょう。
正当な理由がなければ、交渉が失敗しやすくなる
客観的な裏付けがないまま家賃の値上げを申し出てしまうと、入居者から「一方的」「強引」と受け取られてしまうおそれがあります。

不動産管理コンサルタント
東 将吾
特に値上げの幅が大きい場合や、現在の家賃が周辺相場と比べて明らかに低いから合わせたい場合などは、入居者の納得を得るためにしっかりとした根拠が必要です。
たとえば「近隣では同じような物件が〇万円で募集されている」「固定資産税が前年より〇円増えた」といった具体的な数字や事実を示してください。
こうした情報の提示で、「実情」に基づいた話し合いがしやすくなります。
2. 契約書と特約条項をもう一度チェックする

不動産管理コンサルタント
東 将吾
家賃の値上げを検討するとき、必ず確認しておきたいのが「契約書の内容」です。
契約の形態や特約(契約書内で特別に取り決められたルール)の有無によって、取れる対応や交渉の可否が変わってくるのです。
そのため、以下から解説するように、交渉を始める前に契約書の内容をしっかり確認しておきましょう。
まず契約形態を確認する
家賃の取り決めには「普通借家契約」と「定期借家契約」の2つの形態があり、それぞれ以下のように更新のルールや対応方法が異なります。
・普通借家契約:更新が前提となる契約で、法定更新が発生することもあります。
・定期借家契約:契約期間が満了すると終了する契約で、原則として更新されません。
また、契約書には「更新の有無」や「更新料」に関する決まりが書かれていることがあります。
たとえば、契約が自動で更新されるタイプ(法定更新)だと、家賃の条件を変えるのが難しくなることがあります。

不動産管理コンサルタント
東 将吾
さらに、更新のたびに「更新料(契約を延長するために支払うお金)」がかかる契約の場合、入居者はその時点ですでに追加の出費を強いられています。
そこに加えて家賃まで引き上げようとすると、負担が一気に大きくなるため、入居者の理解を得るのが難しくなるかもしれません。
特約で値上げが制限されていないかを見る
契約書に「賃料の改定は行わない」「〇年間は賃料を据え置く」などの特別な取り決め(特約)が記載されている場合、値上げ交渉に影響する可能性があります。

不動産管理コンサルタント
東 将吾
このような特約があると、たとえ借地借家法で値上げ請求が可能であっても、一定期間はその権利を行使できないことになるのです。
特約があると交渉そのものが無効になる場合もある
特約条項には法的拘束力があるため、「契約書に特約が書いてあるけれど、交渉すれば何とかなるだろう」と安易に判断して進めるのは危険です。

不動産管理コンサルタント
東 将吾
契約で値上げを制限している内容が明記されていれば、交渉そのものが無効になってしまうこともあるのです。
事前にしっかり契約書内の特約を読み返し、必要であれば専門家への相談も視野に入れておきましょう。
3. 家賃相場と自物件の条件を比較する
家賃の値上げを検討する際は、「本当にこの物件に値上げの妥当性があるのか?」を客観的に確認することが欠かせません。
ここから解説する方法で、周辺エリアの賃貸相場と、自分の物件の条件を冷静に見比べれば、交渉の根拠としての説得力も高まるでしょう。
比較対象となる物件を選ぶ
まずは、自分の物件と条件の近い物件を探してみましょう。
以下のような「項目が似ている物件」を選ぶと、比較としての信頼性が高まります。
・築年数
・間取り・専有面積
・駅からの距離(徒歩〇分以内など)

不動産管理コンサルタント
東 将吾
こうした条件がそろっていれば、「似たような物件でこの家賃なら、自分の物件も見直していいはず」といった判断がしやすくなります。
そのため、入居者にとっても納得しやすい比較材料になるでしょう。
また、比較時には以下のことに注意しましょう。
条件が異なると比較の意味が薄れる
たとえば、築10年の物件と築30年の物件では、同じ家賃でも印象がまったく違います。
このように、条件が大きく異なる物件と比較してしまったのでは、説得材料としての効果が薄くなってしまうでしょう。

不動産管理コンサルタント
東 将吾
逆に、条件がよく似た物件を比較対象にすることで、入居者から見ても納得しやすいデータになるのです。
比較表を作る
物件ごとの条件を目で見て整理できるよう、簡単な比較表を自作しておくのも大切です。

不動産管理コンサルタント
東 将吾
交渉時に「うちの物件はこれだけ他と違う」と具体的に示せると、入居者にも値上げの理由が伝わりやすくなります。
表には、以下のような項目を入れるとわかりやすいです。
・物件名
・築年数
・間取り・専有面積
・最寄駅・徒歩分数
・月額賃料
各項目については、集めた資料から3〜5件ほどはピックアップし、自分の物件と並べて比較できる形にしておきましょう。
比較表があると入居者への説明もスムーズになる
物件の比較表により、「近隣の物件よりも家賃が明らかに安い」「うちの物件だけ相場から大きくズレている」といった事実を数字と表で示せれば、入居者も値上げに対して納得しやすくなります。

不動産管理コンサルタント
東 将吾
口頭だけで伝えるよりも説得力があり、交渉をスムーズに進める助けにもなるでしょう。
家賃値上げの通知~拒否された場合の対応フロー
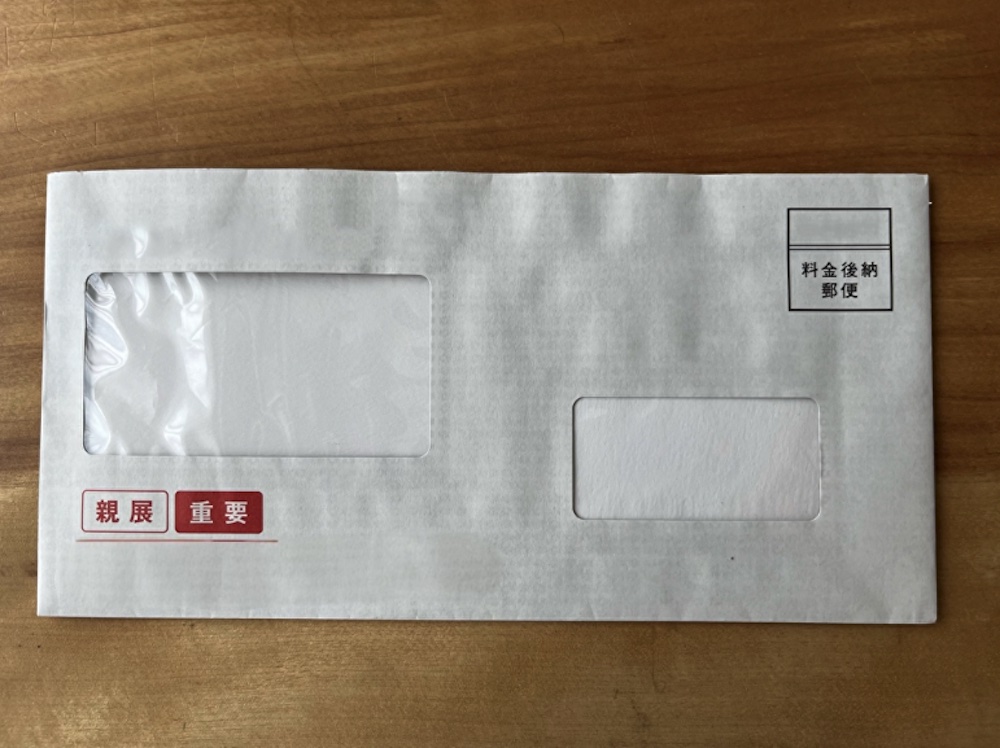
家賃の値上げは一方的に決定できるものではなく、入居者の合意がなければ成立しません。
そのため、値上げの通知後に拒否されるケースも想定しながら、段階ごとに冷静に対応していくことが大切です。
家賃を値上げするまでの、一連の流れは以下3つのステップになります。
・ステップ1:家賃を上げたいときは、まずは丁寧に通知する
・ステップ2:通知が入居者に断られたら、冷静に次の手を考える
・ステップ3:それでも値上げに合意されなければ法的手段に移る
ここからは、それぞれのステップを詳しく見ていきましょう。
ステップ1:家賃を上げたいときは、まずは丁寧に通知する
家賃の値上げを正式に進めるには、まずは入居者に対してその旨を伝える「通知」が必要です。

不動産管理コンサルタント
東 将吾
この段階での伝え方ひとつで、その後の交渉の流れや入居者の反応が大きく変わるため、入居者を焦らせず、誠実な姿勢で臨みましょう。
【文例あり】内容証明は調停や裁判を見据えた場面で有効
賃料の値上げについての打診(協議)は、多くの賃貸借契約書において「協議により変更できる」との定めがあり、原則としていつでも行うことが可能です。
ただし、実務上は契約の更新時期にあわせて行うのが一般的です。
なお、更新時に値上げを申し入れる場合、そのタイミングとしてはおおむね6か月前から2か月前までに通知するのが望ましいとされています。
これは、借主にとって引っ越しや契約見直しの検討期間を確保できるためです。
初回の打診では、柔らかい文面の書面または口頭での説明から始めるケースが多いです。
一方で、入居者からの返答がない・拒否が続くなど進展が見られない場合や、将来的に調停・裁判を見据える場合には、証拠性を高めるために内容証明郵便での通知が有効と言えます。
以下は、そうした場合に備えて使用できる通知文の文例です。
令和◯年◯月◯日
○○○○ 様
(入居者の氏名・住所)
東京都○○区○○町○丁目○番地
〇〇ビル〇〇号室(賃貸物件の所在地)
通知人:山田 太郎
東京都△△区△△町△丁目△番地
電話番号:03-XXXX-XXXX
件名:賃貸借契約の条件変更に関する通知
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、貴殿と私との間で締結した下記物件に関する賃貸借契約(以下「本契約」といいます)について、契約期間満了に伴い、以下のとおり契約条件の変更をご通知申し上げます。
【賃貸物件】
東京都○○区○○町○丁目○番地 ○○ビル○号室
【契約期間】
令和◯年◯月◯日 ~ 令和◯年◯月◯日(契約満了日)
本契約は、令和◯年◯月◯日をもって契約期間が満了いたしますが、引き続き賃貸借契約を継続される場合には、以下の新条件を適用した上で契約更新のご協議をさせていただきたく存じます。
【新賃料(家賃)】
現行:月額80,000円(共益費込み)
変更後:月額88,000円(共益費込み)
【その他条件変更の有無】
共益費・敷金・礼金・契約期間等に変更はありません。
なお、本通知は契約満了日の4か月前にあたる日付にて行っております。ご理解・ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
ご不明点がございましたら、上記連絡先までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
敬具
送付時には、以下のような書類をあらかじめ手元にそろえておきましょう。
・賃貸借契約書
・登記簿(所有者を示す書類)
・固定資産税や都市計画税の通知書

不動産管理コンサルタント
東 将吾
こうした書類は、通知の根拠となる事実を自分で確認するためのものであり、必要に応じて内容を文書に反映させる際にも役立ちます。
また、後から入居者に「根拠を見せてほしい」と言われたときにも、冷静に対応しやすくなるでしょう。
値上げの理由は数字を使ってわかりやすく説明する
通知文には、値上げの理由を具体的な数字で説明することが不可欠です。
たとえば、以下のように示しましょう。
・固定資産税が「年間○円」上がった
・周辺エリアの家賃相場より「月○円」低い状態である

不動産管理コンサルタント
東 将吾
このように、データに基づいた説明をすることで「値上げに対して納得できる理由」が伝わりやすくなります。
抽象的な言い回し(例:「維持費がかかっていて…」)は避け、必要に応じて「数字の根拠もありますよ」と伝えるだけでも、納得感につながるはず。
相手のメリットになる提案を添える
単なる「家賃アップ」だけを一方的に伝えてしまうと、入居者は納得できずに不信感を抱いたり、話し合い自体を拒否するケースもあります。

不動産管理コンサルタント
東 将吾
値上げとあわせて、入居者にとってのメリットや配慮も同時に提示することが大切です。
たとえば、以下のような「妥協案」があると、交渉が前向きになりやすくなります。
・更新料の免除
・インターネット無料化(Wi‑Fi環境の提供)
・設備のグレードアップ(例:エアコン新調)
・防犯設備の追加(モニター付きインターホンなど)
こうした提案によって、入居者は「ただ負担が増えるのではなく、配慮のある対応をしてくれている」と感じやすくなり、話し合いもスムーズに進みやすくなります。
ステップ2:通知が入居者に断られたら、冷静に次の手を考える
家賃の値上げを通知した後、入居者から「納得できない」と拒否されるケースは少なくありません。

不動産管理コンサルタント
東 将吾
これはトラブルではなく、借主側に認められた正当な権利に基づく行動です。
まずは、冷静に受け止めたうえで、次の選択肢を整理しながら、対応を進めていきましょう。
まずは拒否されても動揺しない
借地借家法第32条では、家賃が不相当だと判断された場合に限り、貸主・借主のいずれからも将来に向けた家賃の増減請求ができると定められています。
ただし、その一方で、借主には「増額請求を拒否する権利」も認められているため、値上げの申し出が受け入れられなかったとしても、それ自体は違法ではありません。

不動産管理コンサルタント
東 将吾
拒否されることは、家賃交渉の中ではよくある流れのひとつです。
「断られた=関係が悪くなった」と受け止める必要はなく、あくまでも話し合いの途中段階として、引き続き、前向きに対応していきましょう。
条件を変えてもう一度話し合う
一度断られたからといって、すぐに交渉を諦める必要はありません。
値上げの幅やタイミング、入居者へのサービスなどを調整したうえで、新たな条件で再提案しましょう。
たとえば、初回通知では提案しなかった、以下のような内容を盛り込むのもひとつの手です。
・家賃の値上げ幅を下げる(例:5,000円→3,000円)
・値上げの実施時期を延期する(例:半年後から反映)
・サービスを追加する(例:Wi‑Fi無料、防犯設備の導入など)

不動産管理コンサルタント
東 将吾
入居者の立場に立って提案内容を見直すことで、歩み寄りのきっかけが生まれる場合もあります。
また、交渉は1回限りで完結するものではありません。
数回にわたってやりとりを重ねることを前提に、柔軟な姿勢で臨みましょう。
法定更新になると、古い条件での契約が続いてしまうこともある
交渉がまとまらず契約期間が終了しても合意に至らなかった場合、契約は「法定更新」となり、これまでの条件がそのまま継続されることになります。
借地借家法第26条では、以下のように示されています。
建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。
引用元:借地借家法(平成三年法律第九十号)
この場合、以下のようなリスクがあります。
・家賃が旧条件のまま据え置かれる
・契約内容を見直す機会が失われる
・更新料が取れない(更新条項がない場合)
・管理費や修繕費の負担増に対して調整ができない
結果的に、収益が圧迫されてしまう可能性もあるため、早めに話し合いの落としどころを見つけることが重要です。
ステップ3:それでも値上げに合意されなければ法的手段に移る
何度か話し合いを重ねても入居者との合意が得られない場合、家賃の増額をめぐる交渉は、法的な手続きへと進むことになります。
ここでは「調停」「裁判」と、段階を踏みながら、家賃値上げのために対応していく流れについて解説します。
まずは調停を申し立てる
調停は簡易裁判所を通して行われます。
裁判ほど堅苦しくなく、入居者と再び話し合うための機会として利用できます。
調停申し立ての概要は、以下の通りです。
・申し立て先:物件所在地を管轄する簡易裁判所
・費用:収入印紙代1,000円~数千円程度+郵便切手代(※内容により変動)
・必要書類:申立書、賃貸借契約書の写し、値上げに関する資料など
・所要期間:数週間~数ヶ月程度

不動産管理コンサルタント
東 将吾
調停は裁判よりも柔軟性があり、第三者(調停委員)を交えて冷静に話し合いができるため、感情的な対立を回避しやすいという特徴があります。
調停がダメなら裁判で解決する
調停でも話がまとまらなかった場合は、最終手段として裁判(家賃増額請求訴訟)を起こすことができます。
裁判の基本情報は、以下の通りとなります。
・所要期間:6か月〜1年程度(内容によって前後)
・費用:印紙代・予納郵券+弁護士費用(着手金で10~20万円が目安)
・必要な準備:相場資料・契約内容・過去のやり取り・税金資料などの客観的な証拠
・判決の流れ:認められた場合、家賃は判決確定後に遡って改定され、差額分の支払いも請求できる

不動産管理コンサルタント
東 将吾
ただし、裁判は時間も費用もかかるうえ、判決まで関係性がこじれやすくなるため、あくまで「最終手段」としての位置づけになります。
費用と回収できる家賃額をしっかり比べて判断しよう
裁判に進む前には、費用と得られる増収のバランスを冷静に確認しておくことが重要です。

不動産管理コンサルタント
東 将吾
感情だけで判断するのではなく、「最終的にいくら増収できるのか」「どのくらいコストがかかるのか」を数字で比較してみましょう。
たとえば、以下のようなシミュレーションをしておくと、判断材料になります。
- 月1万円の値上げを36ヶ月回収できる場合:1万円 × 36ヶ月 = 36万円の増収
- 裁判費用(例:印紙代・郵便代など数万円)+ 弁護士費用(着手金約10〜20万円+報酬)=50万円~100万円
このように、想定される利益とコストを比較することで、裁判に進む判断が経済的に妥当かどうかを事前に見極めることができます。
※法的な交渉の相談・対応については弁護士に相談してください。
家賃値上げを拒否されたときによくある質問(FAQ)
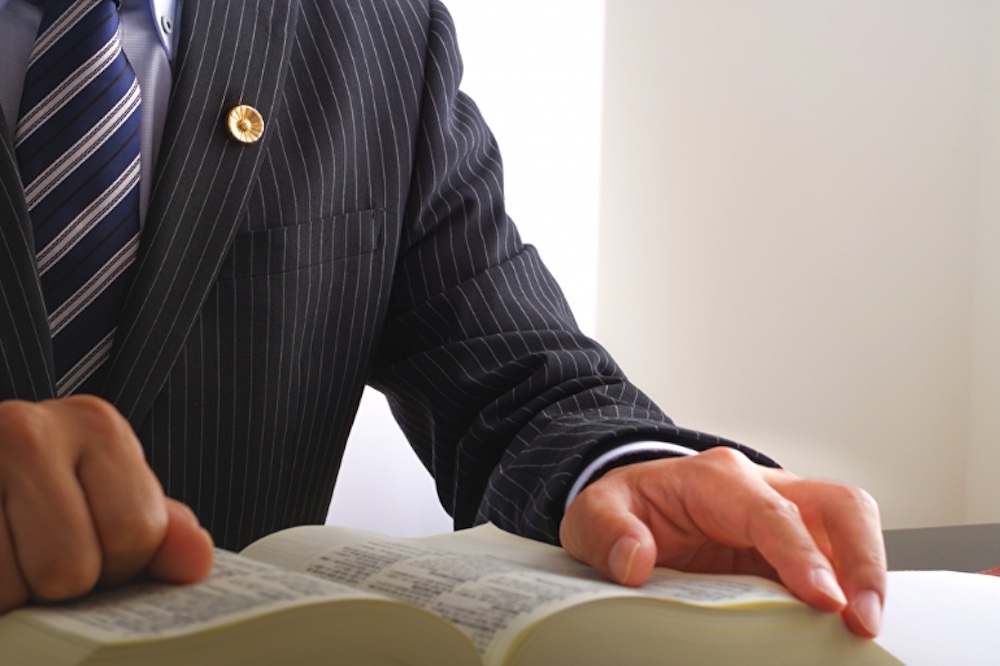
家賃の値上げをめぐるやり取りには、法律や手続き、交渉方法など慣れないポイントも多く、「これってどうすればいいの?」と疑問に感じる方も多いはずです。
家賃値上げが拒否されたケースで、よくある質問は次の通りです。
- 入居者が値上げを断ってきたら、どうすればいいですか?
- 家賃はどれくらいまで上げられるのでしょうか?
- 通知はメールでも大丈夫ですか?
- 調停ってどんなものですか?
- 専門家に相談すべきタイミングはいつですか?
以下からは、1つずつQ&A形式で見ていきましょう。
入居者が値上げを断ってきたら、どうすればいいですか?
入居者から家賃値上げの申し出を断られることは、決して珍しいことではありません。
法律上、借主には増額請求を拒否する権利があるため、値上げがすぐに通らないのは当然の流れでもあります。
ただし、それで終わりというわけではなく、以下のように対応の選択肢は複数あります。
- 条件を見直して再提案する(値上げ幅・時期・付加サービスなど)
- 話し合いで折り合いがつかなければ、調停を申し立てる
- 調停でもまとまらない場合は裁判に進む

不動産管理コンサルタント
東 将吾
このように、「拒否された=打つ手がない」わけではなく、家賃値上げ交渉はまだ続けられる段階にある、ということを前向きにとらえましょう。
家賃はどれくらいまで上げられるのでしょうか?
家賃の値上げについて、法律上「◯%まで」という明確な上限はありません。
しかし、実際には近隣の家賃相場とのバランスが重視されます。
たとえば、同じエリア・同じ間取り・築年数が近い物件と比べて、明らかに現在の賃料が安すぎるような場合には、一定の増額が認められる可能性があります。
目安としては、相場より大きくかけ離れた金額でない限り、5,000円〜1万円程度の上げ幅であれば、入居者にも受け入れてもらいやすいはずです。

不動産管理コンサルタント
東 将吾
最終的には、場と整合性があるかどうか+入居者との合意がポイントになります。
通知はメールでも大丈夫ですか?
いいえ、正式な通知としては書面(特に内容証明郵便)で行うのが基本です。

不動産管理コンサルタント
東 将吾
家賃の値上げを伝える際、「きちんと伝えた証拠は残るし、入居者には値上げをメールで伝えればいいかな?」と考える方はいると思います。
しかし、メールや口頭でのやり取りは記録としての信頼性が低く、「言った・言わない」のトラブルにつながりやすくなるのです。
特に今後、調停や裁判など法的な場面に進む可能性がある場合は、誰が・いつ・どんな内容で通知したかが明確に残る手段を選ぶ必要があります。
そのため、値上げ通知は内容証明郵便など、公的に証明が残る方法で行いましょう。
調停ってどんなものですか?
調停とは、裁判所を通じて入居者と話し合いを行う手続きで、裁判よりも柔らかく、話し合いに近い形で進められる解決方法です。
第三者である調停委員が間に入り、双方の意見を整理しながら、合意点を探っていきます。

不動産管理コンサルタント
東 将吾
調停は、裁判よりも時間や費用の負担が少なく、入居者との関係を大きくこじらせずに済むというメリットもあります。
話し合いが難航してきた場合の、次の一手として検討するといいでしょう。
専門家に相談すべきタイミングはいつですか?
不安があったら、早めに不動産や法律の専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。
家賃の値上げ交渉は、感情や関係性も絡むため、個人での対応に限界を感じる場面も出てきます。
たとえば、以下のタイミングが相談の目安になります。
- 再交渉がうまく進まず、平行線のまま話が止まっている
- 調停を申し立てようと考えている
- 契約内容や法的な判断に自信が持てない
- 裁判を検討しているが、費用や手続きに不安がある

不動産管理コンサルタント
東 将吾
専門家に相談することで、客観的な視点や現実的な対応策が示されるため、無用なトラブルを防ぎやすくなります。
トラブルが大きくなる前に、早めの相談を意識しておきましょう。
家賃の値上げがうまくいかないときには、不動産のプロに任せよう!

今回は、家賃値上げをめぐる交渉・拒否・調停・裁判までの一般的な対応フローを解説しました。

不動産管理コンサルタント
東 将吾
家賃値上げには、正当な理由の整理、入居者との冷静な交渉、そして法的手続きの検討など、段階ごとの対応が重要です。
しかし、不動産経営をすべて一人で背負い込む必要はありません。
交渉が長引いていたり、管理会社が動いてくれなかったり、手続きが複雑で不安な方も多いはずです。
そんなときは、家賃の値上げにお困りの方は「Vision Bridge」にご相談ください。
累計150棟超の取引実績を持つ一棟賃貸専門の不動産会社として、富裕層オーナー向けの課題に多数対応してきた実績があります。
不動産管理の専門資格を持つスタッフが、完全成果報酬制・初回相談無料でサポートいたします。
「本業と両立したい」「トラブル対応に、これ以上時間を取られたくない」と感じたときは、無理をせず、ぜひプロの知見を活用してみてください。
※法的な交渉の相談・対応については弁護士に相談してください。